
毎年秋の2週間には「読書週間」という期間が設けられています。
実は読書週間は、本に触れる絶好のチャンスなんです。
今回は「読書週間」についてアシストします。
- 読書週間について詳しく知りたい人
- 読書週間ではどんな活動が行われているのか気になる人
- 読書週間にピッタリな本を選びたい人
このような方におすすめの内容です。
本記事を読めば、読書週間に本を手に取ってみたくなりますよ!
読書週間の詳細を知ろう【いつ・何をしているの】

まずは読書週間がどのようなものか解説します。
2025年度の読書週間の概要は次のとおりです。
- 回数:第79回
- 期間:10月27日(月)~11月9日(日)
- 標語:こころとあたまの、深呼吸。
読書週間の期間は10月27日から11月9日までと、毎年同じ日付です。
ただ、標語とポスターのイラストは年ごとに募集され、毎年違うものとなっています
読書週間を主催している「公益法人 読書推進運動協議会」によると、読書週間が設けられた経緯は次のとおりです。
終戦まもない1947年(昭和22)年、まだ戦火の傷痕が至るところに残っているなかで「読書の力によって、平和な文化国家を作ろう」という決意のもと、出版社・取次会社・書店と公共図書館、そして新聞・放送のマスコミ機関も加わって、11月17日から、第1回『読書週間』が開催されました。
(中略)
翌年の第2回からは期間も10月27日~11月9日(文化の日を中心にした2週間)と定められ、この運動は全国に拡がっていきました。
公益法人 読書推進運動協議会HPより
つまり読書週間は、戦後、平和な国家を作りたいという願いから始まった活動なんです。
現在、読書週間の主な活動としては
- 読書推進運動協議会HPよりポスターを発送
- 各都道府県また市町村での読書推進
- 図書館や学校などで本に関したイベント開催
といったものが挙げられます。
活動内容が気になった方は、地元自治体や図書館のHP、掲示物を確認してみましょう。
「こどもの読書週間」もある!読書のきっかけ作りに

秋に行われる読書週間の詳細を紹介しましたが、実は「こどもの読書週間」も設けられています。
2025年度の「こどもの読書週間」の概要は次のとおりです。
- 回数:第67回
- 期間:4月23日~5月12日
- 標語:あいことばは ヒ・ラ・ケ・ホ・ン!
「こどもの読書週間」は2000年に現在の春の期間に設定されました。
4月から5月にかけては「国際子どもの本の日(4月2日)」や「サン・ジョルディの日(4月23日、『本の日』とも呼ばれている)」といった記念日が制定されているためです。
子どもが読書に取り組むきっかけになりやすい季節なので、「初めて子どもが本に触れる」というタイミングにピッタリなんです。
「こどもの読書週間」をきっかけに、お子さんだけでなく親も本に触れてみましょう。
以下の記事では「親子読書」のやり方について解説しています。
親子で本を読む際の参考にしてみてください。
【年代別】読書週間におすすめの本を紹介!

ここからは読書週間におすすめの本を、年代別に紹介します。
どの作品も、私が実際に読んで面白いと感じたものです。
ぜひ読書週間をきっかけに触れてみてください。
【小学校低学年向け】らいおんみどりの日ようび/中川李枝子
小学校低学年におすすめの作品は、中川李枝子氏の『らいおんみどりの日ようび』です。
【広告】
本作は、キャベツが好きな緑色のライオン・らいおんみどりが主人公の物語です。
らいおんみどりはトランプが得意。
そこで様々な仲間とともにサーカスを始めるという、想像力を刺激される内容になっています。
小学校低学年では、まず読書に慣れ、楽しんで読書をすることが一番の目的です。
低学年のうちに読書に慣れておくと読解力が育ち、学校の授業にもスムーズに対応できます。
また集中力も身につきます。
『らいおんみどりの日ようび』は、ひらがなが多かったりルビが振ってあったりと、読みやすいが特徴。
私も小学校低学年時代の読書の入り口は『らいおんみどりの日ようび』でした。
ぜひ親子のコミュニケーションのきっかけにしてみてください。
【小学校高学年向け】シートン動物記 オオカミ王ロボ/アーネスト・T・シートン
小学校高学年におすすめの作品は、アーネスト・T・シートン氏の『シートン動物記 オオカミ王ロボ』です。
【広告】
シートンが書いた「シートン動物記シリーズ」の中でも、特におすすめの1冊です。
アメリカのニューメキシコ州にあるカランポー平原。
そこでは放牧された牛が、オオカミ・ロボに襲われる事件が多発していました。
毒の入ったエサや罠にも動じないロボを、いかにして捕獲したのか?
ロボと人間の知恵比べや、ロボの格好良さが光る作品になっています。
小学校高学年になると、だんだんと感性が育ちます。
興味の範囲が広がり、自分が好きな物事もハッキリしてきますよね。
でも「何にも興味を持ってくれない……」という心配を抱えた親御さんや「興味がある物事がない」という悩みを抱えたお子さんも多いはず。
そこで読んでほしいのが本作です。
私は『シートン動物記 オオカミ王ロボ』を読んで、動物に興味を持ちました。
今でも動物自体に興味があり、動物に関するニュースは欠かさずチェックしています。
「興味を持てる物事がない」と悩んでいるお子さんにとって、動物に興味を持てるきっかけにもなる本作。
親御さんからお子さんにおすすめしてみてください。
また「シートン動物記シリーズ」の入り口としてもおすすめの1冊になっています。
【中学生向け】西の魔女が死んだ/梨木香歩
中学生におすすめの作品は、梨木香歩氏の『西の魔女が死んだ』です。
【広告】
本作の主人公は中学生の「まい」。
「まい」は中学に進んでから間もなく、学校へ行けなくなります。
どうしても学校に行けない「まい」は、初夏へと向かう季節に、母方のおばあちゃんの所へ行くことに。
ただ、おばあちゃんは「西の魔女」とも呼ばれていて――というのが物語の始まりです。
おばあちゃんこと「西の魔女」の元で過ごすうち、「まい」は自分を取り戻していきます。
中学生になると思春期真っ只中で、多感な時期でもあります。
学校や家でのストレスが多いのも中学生時代の特徴です。
そんな中学生におすすめしたいのが本作。
主人公「まい」が成長するペースは緩やかですが、確実なものです。
もし中学生のお子さんがいる親御さんなら、ぜひ『西の魔女が死んだ』をお子さんに薦めてみてください。
そして、あなた自身が中学生なら『西の魔女が死んだ』は心の拠り所になる作品となります。
「まい」とおばあちゃんの交流と関係性に、きっと涙するはずです。
本作は文庫版に、メインストーリーの後日談「渡りの一日」が掲載されています。
ページをめくる感覚を味わうためにも、紙の文庫版がおすすめです。
【高校生向け】神さまのいる書店 まほろばの夏/三萩せんや
高校生におすすめの作品は、三萩せんや氏の『神さまのいる書店 まほろばの夏』です。
【広告】
本作の主人公は高校生の「紙山ヨミ」。
ヨミは本が大好きですが、学校でも家庭でも人間関係がうまくいかず、図書室にいることがほとんどでした。
夏のある日、ヨミは司書教諭の紹介で、とある書店で働くことになります。
しかし紹介された書店で扱っていたのは、魂が宿った本「まほろ本」だった――という内容です。
書店で働き始めたヨミは、働く中で様々な障害にぶつかります。
特に苦労するのが「本の補修作業」。
壊滅的に不器用だったヨミは、本を補修しようとしても、補修前よりもメチャクチャにしてしまいます。
でもヨミは諦めません。
同居しているものの苦手意識を持っていた姉に教えを請い、知識を身につけ、見事に本の修復を成功させます。
高校生でバイトデビューを果たす方は多いと思います。
自分でお金を稼げるようになると、嬉しさを感じるはず。
ただ、バイトも嬉しいことばかりではありません。
仕事内容が難しかったり、職場の人間関係で苦労したり。
そんな高校生に本作はおすすめ。
ヨミの感じた達成感は、きっと読者であるあなたも感じられます。
「バイトデビューが不安」と感じている方の心も、少し軽くなる作品です。
【大学生・20代向け】刹那の風景1 68番目の元勇者と獣人の弟子/緑青・薄浅黄
大学生・20代におすすめの作品は、緑青・薄浅黄氏の『刹那の風景1 68番目の元勇者と獣人の弟子』です。
【広告】
主人公・刹那(せつな)は、病が治らず、病院で息を引き取ります。
ただ次の瞬間には、異世界で勇者として迎えられました。
ところが転生した異世界でも病気に罹り、病室のベッドで1年あまりを過ごしていました。
そこにある人物が訪れたことから、刹那の人生は転機を迎える――という内容です。
成人年齢が引き下げられたこともあり、高校卒業と同時に社会人デビューする方もいます。
また大学という新しい環境でも覚えることが多く、家に帰ると疲れ果ててしまう方も。
そんな方に『刹那の風景』は癒しを与えてくれます。
『刹那の風景』は、今流行りの「異世界転生もの」の作品です。
ただ、文体は落ち着いていて読みやすいのが特徴。
さらに世界観も早い段階で把握できるので「異世界転生ものが初めて」という方にもおすすめです。
現在も続いているシリーズなので、まず第1巻目である本作を読んでみて、続きを読むか決めましょう。
【30代向け】スープ屋しずくの謎解き朝ごはん/友井羊
30代におすすめの作品は、友井羊氏の『スープ屋しずくの謎解き朝ごはん』です。
【広告】
『スープ屋しずくの謎解き朝ごはん』の主人公は、話によって変わります。
それでも共通しているのは、スープ屋の店主・麻野が、客として訪れた人物が抱える「謎」を解き明かしていく、という流れです。
謎といっても、警察が関わるような事件ではありません。
ポーチや指輪を失くしたり、人間関係の不和だったりという「日常にある謎」です。
それでも謎の当事者となった人物は、強い不安やストレスを感じます。
麻野はそんな謎の当事者となった客の気持ちを、自身の推理力と特製スープで解きほぐしていくのです。
30代は転職や結婚など、人生の転換期でもあります。
かかるストレスも増大し、日々を生きるだけで精一杯になることも。
でも『スープ屋しずくの謎解き朝ごはん』は、穏やかな文体で読んでいるだけで心がほぐれていく作品です。
また本作は麻野の推理力もさることながら、登場する料理も魅力的です。
そして読み終わった後は必ず、美味しいスープが飲みたくなります。
自身の「食」も見直せる作品なので、美味しいスープを飲みながらストレス解消として本作を読んでみましょう。
【40代以上向け】三毛猫ホームズの推理/赤川次郎
40代におすすめの作品は、赤川次郎氏の『三毛猫ホームズの推理』です。
【広告】
40代以上になると、仕事にも慣れ、新しい刺激が欲しくなる時期でもあります。
そんな40代以上の方におすすめなのが、赤川次郎氏の作品『三毛猫ホームズの推理』。
正確には「三毛猫ホームズ」シリーズ全般です。
「三毛猫ホームズ」シリーズの主役は、タイトル通り「ホームズ」という名の三毛猫です。
ただ、猫であるホームズだけでは、起こった事件を解決できません。
そこでキーパーソンになるのが、血・アルコール・女性が苦手な刑事・片山です。
片山がホームズの動きやしぐさからヒントを得て、見事に事件を解決に導いていく。
「三毛猫ホームズ」シリーズはそんな流れになっています。
第1作目の『三毛猫ホームズの推理』は、以降の作品よりも内容が重めに設定されています。
それでも『三毛猫ホームズの推理』を読んだら、ぜひ2作目の『三毛猫ホームズの追跡』を読んでみてください。
『三毛猫ホームズの追跡』は『三毛猫ホームズの推理』よりも幾分軽めの内容になっているので、2作品続けて読むのが個人的にはおすすめ。
日常生活では味わえないスリルやロジカルな推理が、本作には凝縮されています。
読書週間をきっかけに「三毛猫ホームズ」の世界を堪能してみましょう。
まとめ:読書週間を本に触れるきっかけに
ここまでご覧いただき、ありがとうございます。
今回は読書週間の詳細や、年代別におすすめの本を紹介しました。
読書週間は本に触れる、いいきっかけになります。
読書週間をきっかけに本に触れ、違った世界を見てみましょう。
新たな驚きが待っていますよ。
それでは、良き読書ライフをお送りください!
【参加中です!ボタンを押していただけると嬉しいです!】
にほんブログ村
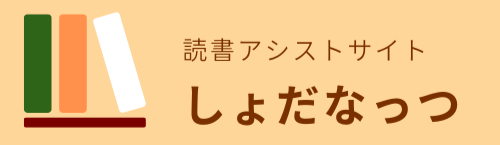







コメント