
あなたは「親子読書」という言葉を聞いたことはありますか?
文字通り「親子で読書を楽しむ」ことです。
でも「読書の時間が取れない」「子どもが読書を嫌がる」といった理由で、親子読書ができないという声も多いですよね。
今回は
- 親子で読書を楽しむ方法が気になる
- 親子読書の具体的なやり方が知りたい
- 子どもが読書を嫌がり、どうしたらいいかわからない
といった「親子読書のやり方」についてアシストします。
今回の記事を読めば、子どもと一緒に読書ができるきっかけがわかりますよ!
【子どもだけじゃない】親子読書のメリット

親子読書のやり方を紹介する前に、親子読書のメリットを知っておきましょう。
親子読書には大きく4つのメリットがあります。
- 読解力が育つ
- 自分で考える力が育つ
- 感受性が豊かになる
- コミュニケーションの機会になる
4つのメリットは子どもだけでなく、親にとってもメリットとなります。
詳しく見ていきましょう。
読解力が育つ
親子読書のメリット1つ目は「読解力が育つ」こと。
読書でもっとも大切なのが「本の内容を読み解く力」です。
「本の内容を読み解く力」は「読解力」とも呼ばれます。
読解力は子どもが元々持っている力ではなく、読書をする中で少しずつ育っていく力なのです。
読解力が育つと、文章を読み解く力が身につき、学校での学習にも役立ちます。
また学校以外でも、新聞といった本以外の読み物を読む際にも役立つんです。
大人である親も同じく、親子読書をする中で読解力は育ちます。
文章の内容を読み解く力は、学校だけでなく大人になってからも必要な力となるので、子どものうちから育てていくことが大切です。
自分で考える力が育つ
親子読書のメリット2つ目は「自分で考える力が育つ」こと。
メリット1で読解力が育つと、次に「自分で考える力」も育ちます。
「自分で考える力」とは、問題にぶつかった時、自分でどうするか考え、決断する力のこと。
自分でどうするか考えるには、物事の本質を見る必要があります。
そして物事の本質を見る練習になるのが読書なのです。
本には作者や著者の考え方・思いが詰まっています。
考え方や思いは、読んでいる本の本質とも言えるため、考え方や思いに触れることで「自分で考える力」が育ちます。
大人である親も、今からでも自分で考える力は身につきます。
ぜひお子さんと一緒に取り組んでみましょう。
感受性が豊かになる
親子読書のメリット3つ目は「感受性が豊かになる」こと。
本にも様々な種類があります。
特に小説は、ハッピーエンドもあれば悲しい終わりを迎えるものも。
様々な小説に触れることで、子どもは次第に感受性が豊かになります。
感受性が豊かになると、相手の立場になった考え方ができ、他人に優しくできるんです。
また様々な考え方があるということも知り、相手を尊重することもできます。
感受性が豊かなことは、生きていくうえで必要な土台です。
読書を通して、子どもだけでなく親であるあなたも、今一度心を養ってみてください。
コミュニケーションの機会になる
親子読書のメリット4つ目は「コミュニケーションの機会になる」こと。
親子読書には親と子どものコミュニケーションが欠かせません。
このあと解説しますが、どんな親子読書のやり方であってもコミュニケーションは必要となります。
そして親子読書は、コミュニケーションの良いきっかけになります。
どんなに親と子どもの時間が合わなくても、読書だけは一緒に行うことで、密な親子の時間を過ごせるんです。
また親子読書の時間を取ることで、子どもは「自分のために時間を作ってくれる」という満足感も得られます。
次第に「自分は大切にされている」という、自己肯定感の基礎も作られるんです。
ぜひ親子読書の時間をコミュニケーションの機会として捉えましょう。
親子読書のやり方4選!【子どもの成長に合わせて】

ここまで親子読書のメリットについて紹介しました。
ではここから、親子読書の具体的なやり方を紹介します。
親子読書は大きく分けて次の4パターンのやり方があります。
- 親が子供へ読み聞かせをする
- 子供が声に出して読み、親が聞く
- 親子で同じ本を別々に読む
- 親子で違う本を読む
子どもの成長に合わせて、親子読書のやり方も変わります。
詳しく見ていきましょう。
親が子どもへ読み聞かせをする
親子読書のやり方1つ目は「親が子どもへ読み聞かせをする」こと。
小学校入学前までの子どもにおすすめの方法です。
最初はシンプルな絵本から始めて、子どもが成長するとともに文字の多い本へとシフトしましょう。
本は子どもが興味を示しそうなものがベスト。
子どもによって興味を示す対象は変わるので、自分の子どもが何に興味を持っているのか探りながら本を選びましょう。
また読み聞かせは、なるべく大きな声でゆっくりと行うのがおすすめ。
「本の絵に見入っている」「楽しそうに次のページを催促する」など、子どもの反応を見ながら読み進めましょう。
子どもが声に出して読み、親が聞く
親子読書のやり方2つ目は「子どもが声に出して読み、親が聞く」こと。
小学校低学年の子どもにおすすめの方法です。
1つ目の方法とは逆に、今度は子どもが読む本の内容を親が聞くやり方となります。
小学校に入学すると、子どもは様々な文章に出会います。
特に国語の授業では、ひらがな・カタカナ・漢字の勉強が進むにつれ、読める本の幅も広がります。
さらに授業では新たな作品にも出会うため、親子読書のきっかけは増えるのです。
そこで子どもに「今は、どんな本を読んでいるの?」と聞いてみて、読み聞かせてほしいとお願いしてみましょう。
子どもは自分の日常に興味を持ってもらえたと嬉しくなり、喜んで読んでくれるはずです。
その際、読み方が分からない言葉があったらフォローを入れたり、途中でつっかかっても温かい目で見守ったりと、けっして子どもを急かさないよう気をつけましょう。
親子で同じ本を別々に読む
親子読書のやり方3つ目は「親子で同じ本を別々に読む」こと。
小学校高学年の子どもにおすすめの方法です。
小学校高学年になると、もう読み聞かせはしなくとも、自立して本を読めるようになります。
そこで親子で同じ本を別々に読むという、親子読書のやり方がおすすめなんです。
同じ本を読んでいるため、親としても安心感があり、子どもにとっては「同じ時間を共有している」という満足感に繋がります。
そしてお互い本が読み終わったら、感想を言い合ってみましょう。
親にとっては子どもの感想が再発見に繋がり、子どもにとっては大人目線の感想のため新たな価値観に触れる良い機会になります。
ただ、どうしても読むペースは親と子どもで違ってしまうため、どちらかが早めに読み終わったら「少し待つこと」という約束も取り入れましょう。
親子で違う本を読む
親子読書のやり方4つ目は「親子で違う本を読む」こと。
中学生以上の子どもにおすすめの方法です。
中学生になると、1人の人間としての自覚が芽生えます。
親としても、それまでと同じ子ども扱いはしませんよね。
そこで親子読書をする際は、お互い違う本を読んで、その感想を言い合う形を取りましょう。
お互い違う本を読んでいるため、双方が新たな発見をするはずです。
時には受け入れられない感想を子どもが持つかもしれませんが、それも承知の上で「なんでそう思ったの?」と子どもに深掘りして聞いてみましょう。
きっと親が想像もしなかった答えが返って来るはずです。
また、中学生になると思春期に入る子どもも多いですよね。
「親子読書なんてウザい!」と子ども拒否するケースもあるので、その場合は強制しないようにしましょう。
親子読書におすすめの本4選!

ここまで親子読書のやり方を紹介しました。

じゃあ、親子読書におすすめの本ってあるの?
本の好みは人によって異なりますが、今回は私が小さい頃に読んで印象的だった本を4冊紹介します。
ぜひ親子読書に取り入れてみてください。
ぐりとぐら/なかがわ りえこ (著)、 おおむら ゆりこ (イラスト)
小学校入学前の子どもとの親子読書におすすめなのが「ぐりとぐら」です。
おそらく親の世代も読んだことがありますよね。
森で大きな卵を見つけたぐりとぐらが、大きなカステラを作るシーンは誰もが一度は憧れたはず。
小学校入学前の子どもへの読み聞かせにピッタリの絵本なので、絵本選びに迷ったらぜひ手に取ってみてください。
【広告】
らいおんみどりの日ようび/中川李枝子
小学校低学年の子どもと一緒に、声に出して楽しみたいのが「らいおんみどりの日ようび」です。
『らいおんみどりの日ようび』は、私も小学生時代に何度も読んだ本でもあります。
キャベツが好きな緑色のライオン・らいおんみどりが主人公の物語で、得意のトランプで、仲間と一緒にサーカスを始めるという内容です。
書かれている文章はひらがなが多く、漢字にルビも振ってあるので読みやすいのが特徴。
想像力をとても刺激される内容なので、子どもが文章の多い本に興味を持ったら、ぜひおすすめしてみてください。
【広告】
シートン動物記 オオカミ王ロボ/アーネスト・T・シートン
小学校高学年の子どもと一緒に同じ作品を読むなら「シートン動物記」シリーズがおすすめです。
「シートン動物記」には様々な話がありますが、特におすすめなのが『オオカミ王ロボ』の話。
アメリカが舞台の話で、放牧された牛がオオカミ・ロボに襲われる事件が続いたことから、ロボをどうやって捕獲するかという、人間とロボの知恵比べが大きな主題です。
一見、嫌われるロボですが、ロボの格好良さが光る作品でもあります。
読む年齢によって感想が分かれる話でもあるので、ぜひお子さんと感想を交えてみてください。
【広告】
西の魔女が死んだ/梨木香歩
中学生以上の子どもとの親子読書におすすめなのが、梨木果歩氏の『西の魔女が死んだ』です。
『西の魔女が死んだ』の主人公も、中学生の少女「まい」のため、同じく中学生のお子さんも感情移入できるはず。
物語の出だしは、いきなり「まい」のおばあちゃんが亡くなったことから始まります。
その後は「まい」とおばあちゃんの思い出が物語のメインです。
文庫本版だと厚さも比較的薄いため、親が先に読み、後で子供が読むという読み方もできます。
大人も感動できる作品なので、ぜひお子さんにもおすすめしてみてください。
【広告】
【気をつけて!】親子読書の注意点

ここまで親子読書におすすめの作品を紹介しました。
最後に、親子読書を行う際の注意点を見ていきましょう。
子どもが楽しめる本を選ぶ
親子読書はあくまで子どもが主役なため、子どもが楽しめる本を選ぶことが大切です。
絵が好きな子どもなら、挿絵が多い本や図鑑などを。
文章が好きな子どもなら、文章が主体の本を選ぶようにしましょう。
また、本にも対象年齢が設定されているため、その年齢を目安に選んでもOK。
子どもがストレスなく楽しめる本を選んで、親子で楽しみましょう。
子どもが嫌がる時は強制しない
昨日までは親子読書を楽しめていたのに、今日は断固拒否。
こんな時もありますよね。
その場合は親子読書を強制せず、子どもが再び「読みたい」と言える日まで待ちましょう。
先ほども書いたように、子どもがストレスなく楽しめるのが親子読書の前提です。
読書を強制した結果、子どもが読書嫌いになってしまっては親子読書どころではなくなります。
子どもが嫌がる時は強制せず、子どもの方から「読みたい」という言葉が出たら、親子読書を再開しましょう。
タブレットも活用しよう
たくさん本を読んであげたいけれど、紙の本を買うと収納場所に困るという親御さんも多いですよね。
そんな時はタブレットを活用しましょう。
以下のような画面が大きめのタブレットなら、小さな子どもでも絵や文字を追うのを楽しめます。
【広告】
またタブレットには絵本や本のデータが何百冊と入るので、紙の本のように収納場所に困るということはありません。
もし家にインターネット環境が整っているのなら、タブレットの購入も考えてみましょう。
ただし、あまりに長時間タブレットを見ると、子どもの目が急速に悪くなります。
また本のデータ以外は見られないようロックをかけるなど、子どもの成長に悪影響の無いよう注意しましょう。
「読んでほしい」という子どもの要求にはできるだけ応じる
子どもが「読みたい」「読んでほしい」という時に、親の時間が取れないという場面もあります。
それでも理想は「読んでほしい」という子どもの要求に、できるだけ応じることです。
子どもと一緒に読書ができる時間は限られています。
まして読み聞かせがメインの小学校入学前は、親子読書は貴重なコミュニケーションの機会です。
もし読み聞かせる本が絵本だった場合は、かかる時間は5~20分程度ですよね。
どうかその時間を惜しまず、子どもの要求にはできるだけ応えるようにしましょう。
時間が取れない場合は代わりとなる日時を約束する
それでも、5分という時間も取れないという場面があるかもしれません。
その場合は代わりとなる日時を子どもと約束しましょう。
今日はどうしても読む時間が取れないという場合は「明日の寝る前なら時間が取れるから、今日は我慢してほしい」という、正直な気持ちを伝えましょう。
親が正直に言っていることは、必ず子どもにも伝わります。
子どもが納得したら、約束した日時に必ず親子読書の時間を取りましょう。
子どもも自分との約束が守られることで「自分は大切にされている」と納得感を得られます。
子どもの心の成長のためにも、親子読書の約束は必ず守りましょう。
まとめ:親子読書で絆を深めよう
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
親子読書は親と子の絆を深める、良い機会です。
ぜひどちらも楽しめる読書の時間を作りましょう。
きっとお子さんも、親であるあなたも満足できるはずですよ。
それでは、良き読書ライフをお送りください!
【参加中です!ボタンを押していただけると嬉しいです!】
にほんブログ村
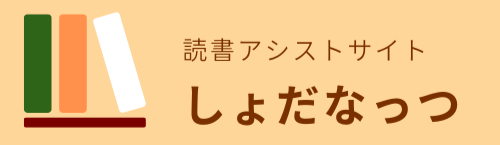




コメント