
本を読む中で「自分が書いた文章も本になればなぁ」と思ったことはありませんか?
難しいとわかっていても、いつかは――と願ってしまう。
実はその願い、叶えられるんです!
今回は「個人で本を出す方法」についてアシストします。
- 自分が書いた文章を本にしたい人
- 本を出版したいけど難しそうと思っている人
- 出版方法や大まかな流れが気になる人
このような方におすすめの内容です。
本記事を読めば、書いた文章を本にする流れがわかりますよ!
【結論】個人でも本は出せる!

結論を先に書くと、個人でも本は出版できます。
紙の書籍の形はもちろん、電子書籍というデータ形式でも出版は可能なんです。
少し前まで、少部数の本は高額な印刷代・出版代などがかかり、個人で本を出すのは高値の花でした。
でも現在は、少部数専門の印刷会社が多くあるため、印刷代なども低く抑えられるようになったのです。
また電子書籍というデータ形式での出版なら、さらに費用を低く抑えられます。
個人で本を出すという夢は、十数年前よりも格段に実現しやすい夢となったのです。
個人で本を出すメリット・デメリットを把握しよう

「個人でも本は出せる」という結論を書きましたが、もちろんメリットとデメリットはあります。
個人で本を出すメリット・デメリットは以下のとおりです。
- 有名でなくても作家デビューができる
- 自分の経験や考えを多くの人に伝えられる
- 利益を追求しない出版ができる
- 出版費用は全額自己負担になる
- 出版物の内容についてトラブルがあった場合、対応する必要がある
- 特約店契約がないと書店に並ばないこともある
メリットの主な特徴は「自分らしい本が出版できる」ということ。
出版した時点で作家デビューでき、自分の経験や考えを、利益を追求しない形で広めることができます。
逆にデメリットの主な特徴は「出版後の対応が大変」ということ。
出版費用は全額自己負担となり、トラブルがあった際も自分で対応する必要があります。
また紙の書籍の場合、特約店契約(新刊は必ず販売するという書店と出版社の取り決め)がないと、書店に本自体が並ばない可能性もあるのです。
個人で本を出す場合は、メリットとデメリットを把握したうえで、出版するかどうか決めましょう。
個人で本を出す方法5選【自分に合った方法で】

では、個人で本を出す方法はどのようなものがあるでしょうか。
今回は代表的な5つの方法を紹介します。
自分に合っていると感じる方法で本を出してみましょう!
自費出版
個人で本を出す方法、1つ目は「自費出版」です。
個人が本を出す際の、代表的な方法です。
そもそも自費出版とは「書籍をはじめとする何らかのメディアで、著者が自分で費用を出して出版すること(ウィキペディアより抜粋)」。
個人で本を出すこと自体が自費出版に当てはまりますが、今回は「紙の書籍で本を出すこと」を自費出版として定義します。
自費出版の流れは次のとおりです。
- 企画・校正を組み立てる
- 原稿や写真・図版を用意する
- デザイン・レイアウトを組む
- 校正・校閲を行い誤植や誤情報を防ぐ
- 印刷・製本され納品
(EDI MAGより抜粋)
自費出版でも、通常の商業出版と同じような流れで本を作ります。
自費出版でポイントとなるのが「部数」。
どのくらいの部数を印刷・製本するかによって、費用も大きく異なります。
のちほど、自費出版サービスを行っている会社も紹介するので、紙の書籍での出版に興味がある方は各社のホームページを確認してみましょう。
(参考:自費出版の流れや製作期間、費用を理解してトラブル回避)
電子書籍
個人で本を出す方法、2つ目は「電子書籍」です。
現在、個人出版のメジャーとなりつつある出版方法でもあります。
電子書籍で本を出版するには、基本的に「表紙画像」「目次」「本文データ」が必要です。
「表紙画像」はプロに依頼するほか、自分で写真を撮影したり絵を描いたりして用意します。
「目次」と「本文データ」は、パソコンに入っている文章作成アプリで作成可能です。
電子書籍の大きなメリットは「出版費用が安い」こと。
紙の書籍と比較すると、電子書籍の方が圧倒的に費用を抑えられます。
また日常的にパソコンを使用している人なら、電子書籍の方が出版にかかる期間も短縮できます。
紙の書籍にするか電子書籍にするかは、個人の好みで別れるポイントです。
パソコンを使用して執筆しているなら、電子書籍での出版も検討してみましょう。
文学フリマ
個人で本を出す方法、3つ目は「文学フリマ」です。
文学フリマとは「作り手が『自らが文学と信じるもの』を自らの手で作品を販売する、文学作品展示即売会」のこと。
小説はもちろん、エッセイ・詩や俳句など、様々なジャンルの文学が出品され、販売されます。
営利・非営利はもちろん、個人・団体も問わず、参加する年代も10代~90代と、幅広い作り手が参加しています。
2025年2月現在、九州〜北海道までの全国8箇所で、年合計9回開催されているのも特徴です。
(概要:文学フリマ公式サイトより抜粋)
文学フリマに出品するには、基本的に紙の書籍形式となります。
ただ、自費出版よりも必要な部数は少なく抑えられるため、費用も自費出版ほどかかりません。
現在は少部数の印刷に特化した印刷会社もあるので、文学フリマへの出品も以前より簡単になっています。
文学フリマへの出品に興味が湧いたら、公式ホームページを確認してみましょう。
出版社への持ち込み
個人で本を出す方法、4つ目は「出版社への持ち込み」です。
インターネットやパソコンが普及するまでは、頻繁に行われた出版方法です。
具体的な方法は単純で、自身の作品を出版社へ持ち込むだけ。
ですが、実際に出版と決まるには、何社も出版社を訪れなくてはなりません。
しかも出版が決まらないという最悪の状況さえありえます。
それでも、自身の作品に熱量と思いがあり「絶対に紙の書籍で出版したい」という信念があるなら、出版社の担当者にくみ取ってもらえる可能性は高まります。
特に原稿用紙に手書きで作成している方は、思い切って出版社への持ち込みも検討してみましょう。
別媒体の経由
個人で本を出す方法、5つ目は「別媒体の経由」です。
今までの出版方法は直接的な方法でしたが、別媒体を経由する間接的な方法もあります。
主な例は以下のとおりです。
- 小説投稿サイトでコンテストに応募する
- 投稿サイトに掲載している作品を有料記事として販売する
- 各種公募に応募する
コンテストや公募に応募し、そこでの受賞をきっかけに本を出版する。
また「note」などの作品投稿サイトで、有料記事として作品を販売する。
直接出版ではありませんが、公募やサイトを経由することで、自分のファンになってくれた方が購入する可能性が高くなります。
またコンテストを受賞すると、そのまま担当者がついて出版というケースもあります。
特に「執筆速度が速い」「継続して作品を投稿し続けている」という方は、このような別媒体経由での出版も視野に入れてみましょう。
本の出版はココで!自費出版サービスを紹介

ここまで個人で本を出す方法を紹介しました。
その中でも紙の書籍での自費出版を目指したいという方に向けて、最後に自費出版サービスを展開している出版社を紹介します。
幻冬舎ルネッサンス
自費出版サービス1つ目は「幻冬舎ルネッサンス」です。
出版社「幻冬舎」が提供している自費出版サービスです。
大きな特徴は「編集と流通に強い」こと。
読者の目線から市場流通を意識して提案を行え、出版目的や読者ターゲットに合わせた作品になるよう、制作・プロモーションチームのサポートを受けられます。
費用は本の仕様や発行部数により異なります。
また推奨発行部数は1,130部~とされています。
「有名な出版社から、書店流通を目的に出版したい」という方は、幻冬舎ルネッサンスを検討してみましょう。
風詠社
自費出版サービス2つ目は「風詠社」です。
風詠社は低コストで本格的な自費出版が可能になるサービスを提供しています。
紙書籍での出版のほか、電子書籍での出版にも対応。
出版費用は「委託配本型」「注文配本型」「私家版」「電子出版」の4パターンがあり、自身の出版形式に近い形での費用が見積れます。
また本が売れた際の印税は、10%~50%と幅広く設定できます。
作者の予算や納期にも柔軟に対応してもらえるため「初めて自費出版をする」という方は、風詠社のサービスを検討してみましょう。
MyISBN
自費出版サービス3つ目は「MyISBN」です。
「MyISBN」の大きな魅力は「税込み5,478円で本が出版できる」こと。
PDFなどのデジタルデータがあれば、編集やデザインを著者自身で行うことで5,478円という安値で本を出版できるんです。
出版した本には、書籍を特定するための国際規格である「ISBN」コードが付与されます。
そのため出版した書籍は全国の書店で買えるほか、ネット通販のAmazonでも購入できるため、販売網が広くなるのです。
「出版費用をなるべく抑えたい」「電子書籍と紙の書籍、両方で出版したい」という方は、「MyISBN」のサービスを検討してみましょう。
まとめ:本を出す夢は叶えられる!
ここまでご覧いただき、ありがとうございます。
今回は「個人で本を出す方法」を紹介しました。
「本を出す」というと「費用がかかる」「売れなかったら……」とマイナスな面が多く、踏み切れなかった方も多いですよね。
でも現在は、そのハードルは十分低くなっています。
ぜひあなたの「本を出したい」という夢を実現させてみましょう!
それでは、良き読書ライフをお送りください!
【参加中です!ボタンを押していただけると嬉しいです!】
にほんブログ村
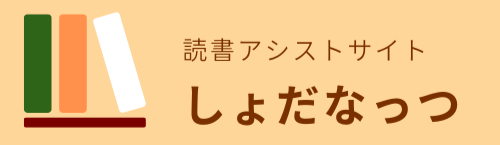



コメント