
読書の相棒である本、ちゃんと管理できていますか?
紙の本は平積みや埃まみれ、電子書籍ならデバイスのストレージ圧迫。
そのままにすると、大切な本を見失ってしまうかも。
今回は「本のおすすめ管理術」についてアシストします。
- 本が床に平積み状態の人
- 電子書籍のデータがストレージを圧迫している人
- 紙派・電子派それぞれにおすすめの管理法が知りたい人
このような方におすすめの内容です。
本記事を読めば、本をきちんと管理できるきっかけになりますよ!
紙の本が多い場合は、本自体の数をまずは減らしてみましょう。
BOOKOFFの宅配買取なら、本を段ボールに詰めて送るだけで完了。
あとは査定を待つだけです。
「本の数が多くて整理できない……」とお悩みの方は、この機会に以下のリンクから詳細をご覧ください!
【広告】
【ブックオフ】公式宅配買取サービス【紙派・電子派】自分の傾向を知ろう

本のおすすめ管理術を紹介する前に、自分が「紙派」なのか「電子派」なのか知っておきましょう。
「紙派」とは、印刷された紙の本を読むことがメインの方を指します。
対して「電子派」とは、スマホやタブレットといったデバイスで、電子書籍を読むことが多い方を指します。
自分が紙派なのか電子派なのかを把握することが、本をしっかり管理する第一歩です。
あなたが「紙の本が多い」と紙派だったら「【紙派におすすめ】本の管理術」から読み始めましょう。
また「電子書籍がメイン」と電子派だったら「【電子派におすすめ】本の管理術」から読み始めてください。
ただ「紙の本も電子書籍も楽しんでいる」という、紙派と電子派の間、という方もいますよね。
その場合は両方の章を読んでみて、取り入れやすい管理術から実践してみましょう。
【紙派におすすめ】本の管理術

まずは紙派の方におすすめの管理術を4つ紹介します。
- カラーボックス+100均グッズを活用する
- また買える本は一旦手放す
- 図書館を活用する
- 読む本の冊数を決める
詳しく解説します。
カラーボックス+100均グッズを活用する
紙派におすすめしたい本の管理術、1つ目は「カラーボックス+100均グッズを活用する」こと。
本の冊数が10~40冊前後という方におすすめの方法です。
カラーボックスは3段あるタイプが一般的です。
その3段を活用して、上から
- 1段目:これから読む本、読んでいる途中の本
- 2段目:読み終わったが半年以内に購入した本、読み返している本
- 3段目:読み終わり半年以上ページを開いていない本
と分けましょう。
そして本を整理する時は3段目のスペースから整理を始めると「読む?読まない?」と迷うことが少なくなります。
結果的にスムーズに本を整理でき、時間も労力も少なく済むのです。
カラーボックスに入れた本は、半年・1年など一定期間で区切り、1段目の本を2段目に、読まなくなった本を3段目へと移動させます。
定期的に本の見直しをすると、より効果的です。
ただ、カラーボックスのスペースに、文庫本といった小さめの本を収納すると余分なスペースができます。
その際は100均ショップに売っているグッズを活用しましょう。
カラーボックスにおすすめのグッズのほか、紙の本の収納におすすめのグッズは以下の記事にまとめました。
ぜひ一度、目を通してみてください。
グッズを組み合わせて、効率よく本を収納しましょう。
また買える本は一旦手放す
紙派におすすめしたい本の管理術、2つ目は「また買える本は一旦手放す」こと。
特に読み終わった本が多いという方におすすめの方法です。
ネット通販サイトやフリマアプリで再度購入できる場合は、思い切ってその本は手放します。
「また買える」の判断は簡単。
まず「Amazon」や「楽天市場(楽天ブックス)」などで本のタイトルを検索します。
検索結果として本の情報が表示され「在庫が十分」「価格が安い・定価」という場合は、再度購入できるという判断ができます。
またフリマアプリでも本のタイトルを入力してみて、出品数が多く売値が安いなら「また買える」という判断になります。
逆に検索結果が「在庫なし」、また価格が定価よりも高い場合、今では手に入りにくい本だと判断できます。
その場合は手元に残すのがおすすめです。
また本を手放す時、手放す冊数が多い場合はBOOKOFFの買取りサービスを利用してみましょう。
BOOKOFFの買取りサービスは段ボール箱に本を詰めて送るだけなので、店舗まで持ち込む手間が省けます。
ブックオフの買取りサービスの詳細を知りたい方は、以下のリンクからご覧ください。
【広告】
図書館を活用する
紙派におすすめしたい本の管理術、3つ目は「図書館を活用する」こと。
状態が良く、貴重な本が多いという方におすすめの方法です。
図書館の多くは「寄贈」というシステムを取り入れています。
「寄贈」とは、図書館がまだ所蔵していない本を、一般の方から無料で譲り受けるシステムのこと。
そこで、図書館に無く、かつ自分が持っている本があるなら「寄贈」システムを利用しましょう。
買取り店と違い、手放した際の料金は発生しません。
ですが「自分が持っていた本が図書館にある」という状態に、喜びを噛みしめられるはずです。
本が片付くのと同時に、適切な場所で管理もされるため、本のためにもなるおすすめの管理術です。
読む本の冊数を決める
紙派におすすめしたい本の管理術、4つ目は「読む本の冊数を決める」こと。
こちらは本を買う前に行う方法です。
「読みたい」という欲求のまま本を買っていくと、当然読み終わった本が部屋に溜まります。
しだいに床に平積みとなり、本に埃が積もる事態に……。
そこで1年や半年で区切りをつけ、読む本の冊数をあらかじめ決めてみましょう。
本の収納場所と相談して「今年は○冊まで」「半年で○冊まで」と決めることで、収納スペースも圧迫しづらくなります。
おすすめは年末の大掃除の際に本を整理して、同時に来年読む冊数を決める方法。
もし年や月の途中で決めた冊数を読み終えてしまったら、本の感想をまとめたり同じ本を再度読んだりするなど、読書に関連した活動を行います。
特に本の感想をまとめてSNSなどで発信すると、新たな読書仲間ができたり、様々な反応がもらえたりと、良い刺激になります。
最初は冊数を決めることに抵抗を感じますが、ぜひ一度試してみてください。
【電子派におすすめ】本の管理術

次は電子派の方におすすめの管理術を4つ紹介します。
- 無料本は読み終わったら削除する
- 1冊読み終えてから次の本を読む
- 大容量のメモリーカードを選ぶ
- デバイス自体を見直す
こちたも詳しく解説します。
無料本は読み終わったら削除する
電子派におすすめしたい本の管理術、1つ目は「無料本は読み終わったら削除する」こと。
いろんな本のデータがごっちゃになっている方におすすめの方法です。
電子派の管理術は「デバイスの空き容量」がカギ。
デバイスの空き容量が多いほど、たくさんの電子書籍データを保存できるためです。
そこでまず、無料でダウンロードした「無料本」のデータは読み終わり次第、削除する癖をつけましょう。
無料本は無料である限り、何度でもダウンロードできます。
そのためデバイスに残す優先度は、自然と低くなります。
手元にどうしても残しておきたい本以外は、読み終わり次第削除するのを習慣にすると、デバイスの空き容量も保てますよ。
1冊読み終えてから次の本を読む
電子派におすすめしたい本の管理術、2つ目は「1冊読み終えてから次の本を読む」こと。
特に中途半端に読んだ本が溜まっている方に、おすすめの方法です。
電子書籍派は手軽に読める一方、気分によって違う書籍をどんどんとダウンロードできます。
すると、最後まで読めていない本が多くなり、データを整理したくても「読み終わっていないから削除できない」という事態になるんです。
これを防ぐためにも「1冊読み終えてから次の本を読む」ようにしましょう。
「1冊読み終えてから次の本を読む」ことを習慣化することで、データを整理する際にも「読んでいないけど、どうしよう?」という迷いがなくなります。
また気持ち的にも区切りがつき、次の読書にもスムーズに移れます。
電子書籍にも、著者・作者の思いが込められています。
1冊を読み終え、区切りをつけることを心がけてみましょう。
大容量のメモリーカードを選ぶ
電子派におすすめしたい本の管理術、3つ目は「大容量のメモリーカードを選ぶ」こと。
データ量の大きな本が多い方におすすめの方法です。
デバイスの多くは、メモリーカードを挿すことで容量を増やせます。
そのため電子書籍が保存できなくなったら、大容量のメモリーカード購入を考えてみましょう。
デバイスによって対応するメモリーカード種類は異なりますが、現在の主流は「microSDカード」です。
1つの目安として、microSDカードの容量が64GBあれば、電子書籍は約800冊保存できます。
そのためmicroSDカードの容量に余裕が欲しい場合は、64GB以上を目安に購入しましょう。
ただし、microSDカードは容量によってカードの規格が変わります。
あなたが持っているデバイスがどの規格のカードに対応しているのか、あらかじめ確認しておきましょう。
購入時の注意点が、メモリーカードの「スピードクラス」です。
スピードクラスはアルファベットの「C」の中に書かれることが多い数字で、大きいほどデータの書き込み速度が上がります。
速度が速いほど、電子書籍を保存する際の時間も短く、待ち時間ストレスも減ります。
おすすめは以下の商品のように、スピードクラスが「10」のもの。
【広告】
「10」あれば平均的な書き込み速度となるため、待ち時間ストレスも少なくなります。
microSDカードなどのメモリーカードを購入する際は
- 手持ちのデバイスに対応している規格のカードか
- 容量は64GB以上あるか
- スピードクラスは10あるか
など、複数のポイントを確認して購入しましょう。
参考URL:よくわかる! SDカードの選び方–GREEN HOUSE
デバイス自体を見直す
電子派におすすめしたい本の管理術、4つ目は「デバイス自体を見直す」こと。
古いデバイスを使い続けている方におすすめの方法です。
microSDカードの容量を増やしたくても、デバイスが対応していない。
またデバイス自体のストレージ容量が少ないという場合は、デバイス本体を見直し、新しいデバイスの購入を検討しましょう。
特に画像や絵の多い写真集・フルカラーの漫画を読んでいる場合、絵の精密さに比例して、電子書籍のデータサイズは大きくなります。
そのためデバイス自体を買い替えた方が、読書もより楽しめるんです。
電子書籍をスマホで楽しんでいる方は、契約しているキャリアのサイトで機種変更を検討しましょう。
またタブレットで読んでいる方は、以下のような普通のタブレットがおすすめです。
【広告】
一般的なタブレットなら、文字の多い小説も、画像が多い漫画もどちらも楽しめます。
スマホもタブレットも、機能的には10年の使用が1つの目安となります。
安い買い物ではありませんが「ストレスなく電子書籍を楽しみたい」という方は、デバイス自体の見直しがおすすめです。
まとめ:本を上手に管理しよう!
ここまでご覧いただき、ありがとうございます。
今回は「本のおすすめ管理術」について紹介しました。
読書の相棒である大切な本。適切に管理することで、あなた自身も読書を長く楽しめますよ。
この機会に、本を上手に管理・整理してみましょう。
それでは、良き読書ライフをお送りください!
【参加中です!ボタンを押していただけると嬉しいです!】
にほんブログ村
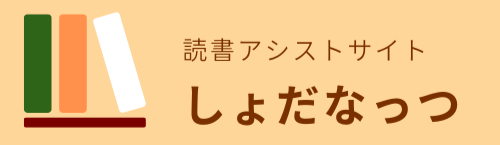




コメント