
あなたは読書の記録をつけていますか?
実は読書記録をつけると、読書がさらに捗るというメリットがあるんです。
でも「読書記録は紙に書いている」人もいれば、「スマホに残している」という人も。
読書記録を始めようとしても、アナログとデジタル、どちらがいいか迷いますよね。
そこで今回は「読書記録はアナログかデジタルか」についてアシスト。
- 読書記録をアナログとデジタルで迷っている人
- アナログとデジタル、両方の特徴を知りたい人
- 読書記録におすすめのツールが気になる人
このような方におすすめの内容です。
本記事を読めば、自分に合った読書記録法がわかって、読んだ本の振り返りに役立ちますよ!
【結論】自分に合う方法でOK!

まず結論を書くと、読書記録は自分に合った方法なら、アナログ・デジタルどちらでも問題ありません。
読書記録は長く続けられるのがベストなため、自分に合った方法で記録するのが一番だからです。
自分がアナログとデジタル、どちらの方法が合っているのかを知るには、まずは両方の方法を試してみましょう。
試す期間は「本○冊分」と決めると比較しやすいです。
アナログとデジタル、両方を試してみて「自分に合っている」と感じた方を選びましょう。
ちなみに私は、アナログとデジタル、両方で読書記録をつけています。
プライベート用はアナログで、外向けに公開するのはデジタルで、という使い分けです。
私と同じように、アナログとデジタルを組み合わせるのもおすすめですよ。
ただ「記録を残すのが面倒」という方は、無理に読書記録をつける必要はありません。
「記録をつけるために読書をする」と、目的が変わってしまうのは良くないからです。
「毎回記録を残すのは面倒」という方は「本当に感動した・役に立った本だけ記録に残す」とすると、記録が重荷にならないので試してみましょう。
【比較】デジタル・アナログの特徴

次はアナログとデジタル、それぞれの特徴を見ていきます。
アナログとデジタルの特徴をまとめると次のようになります。
| メリット | デメリット | |
| アナログ | ・「書く」こと自体が良質なアウトプットになる ・記録が溜まっていくことが満足感になる | ・長く続けていくと保管のための場所が必要 ・簡単に内容の修正ができない |
| デジタル | ・内容の修正が簡単 ・保管のための場所をとらない | ・誤操作で内容が簡単に消えてしまう ・デジタル端末を持っていないと記録できない |
アナログの読書記録の特徴は「満足感を味わえる」こと。
実際に紙に書くことで満足感に浸れ、同時に「書く」こと自体が良いアウトプットになります。
ただ、内容を書き直すには一度消すという手間がかかること。
また記録を保管するための場所が必要になるので注意しましょう。
対して、デジタルの読書記録の特徴は「データで保管できる」こと。
記録をデータで残すため内容の修正が簡単で、保管のための場所も取りません。
ただ、データのため簡単に消えてしまう可能性があること。
また、スマホやパソコンといったデジタル端末を持っていないと記録できないので、必要に応じて用意しましょう。
読書記録のおすすめツール【アナログ編】

ここからはアナログ・デジタルそれぞれにおすすめの記録ツールを紹介します。
まずはアナログの読書記録におすすめのツールです。
読書記録用メモ・ノート
アナログの読書記録におすすめのツール、1つ目は「読書記録用メモ・ノート」です。
アナログで読書記録をつけるとき、必ず必要なのが紙とペンです。
ペンは書きやすいものや、フリクションボールペンといった修正が簡単にできるものがおすすめ。
そして記録する紙は、できれば専用のメモやノートだと記録しやすいです。
読書記録専用のメモ帳やノートなら、書く項目が決まっているため「何を書けばいいかわからない」という方にもおすすめ。
私も実際に、プライベート用の記録は以下のような専用のメモ帳に記録をしています。
【広告】
項目が決まっていると、過去の記録と簡単に比較でき、振り返りもしやすいです。
サイズもコンパクトなものが多いため、アナログの記録に迷ったら、まず専用のメモ帳やノートを取り入れてみましょう。
レポート用紙・ルーズリーフ
アナログの読書記録におすすめのツール、2つ目は「レポート用紙・ルーズリーフ」です。
特にビジネス書や自己啓発本の記録を残すのに、おすすめのツールでもあります。
レポート用紙やルーズリーフの使い方について詳しく書かれているのが、私も参考にした印南敦史(いんなみ あつし)氏の『遅読家のための読書術』です。
【広告】
簡単に説明すると「本の内容で大切だと感じた一文を、レポート用紙やルーズリーフにまとめていく」となります。
『遅読家のための読書術』ではレポート用紙を推奨していますが、家にルーズリーフが余っていればそちらも活用できます。
そして本を読み終わったら、用紙に書いた一文の中から「コレ!」という一文に印をつけるのです。
その一文は自分にとって、もっとも大切な部分ということになります。
『遅読家のための読書術』では、さらにその一文をまとめることを勧めています。
ただそこまで余裕がない方は、単に本の内容をまとめた用紙だけでも、読み返すだけで本の内容を思い出せますよ。
家にレポート用紙やルーズリーフが余っていたら、ビジネス書や自己啓発本の記録に役立ててみましょう。
大きめの付箋
アナログの読書記録におすすめのツール、3つ目は「大きめの付箋(ふせん)」です。
先ほど紹介した「レポート用紙・ルーズリーフ」の応用版です。
やり方は簡単。
大きめの付箋を用意して、心に響いた一文を付箋に書き、ノートに貼っていくだけ。
付箋に書くことで、消せないペンを使っていても付箋を変えることで、ノートに直接書くよりも簡単に書き直せます。
ノートが付箋でいっぱいになったら「レポート用紙・ルーズリーフ」と同じように「コレ!」という文章に印をつけましょう。
その一文が、あなたにとってもっとも大切な内容だとわかります。
また付箋を貼り終わって眺めると「自分はこういう文章が好きなんだ」と、好きな文章の傾向もわかるんです。
大きめの付箋は、100均ショップや文房具店などで手軽に買えます。
家に余っているという場合も、ぜひ活用してみましょう。
カレンダー
アナログの読書記録におすすめのツール、4つ目は「カレンダー」です。
ここまで「本の内容や感想を書く」方法を紹介しましたが、それも面倒という方もいますよね。
その場合は「本が読めたらカレンダーに印をつける」という方法を試しましょう。
カレンダーに印をつけるだけと、簡単に実践できるのでおすすめです。
印をつけることに慣れてきたら、これまで紹介したおすすめツールを購入するという選択もできます。
「まずは読書自体に慣れたい」という方は、簡単にできる「カレンダーに印」方法を取り入れてみましょう。
読書記録のおすすめツール【デジタル編】
次にデジタルの読書記録におすすめのツールを紹介します。
こちらはスマホやパソコンなどのデジタル機器を、すでに持っていることを前提とします。
メモアプリ
デジタルの読書記録におすすめのツール、1つ目は「メモアプリ」です。
メモアプリはパソコンやスマホにすでに入っている場合が多いので、それを活用しましょう。
記録する内容は
- 読み終わった日付
- 本のタイトル
- 著者名
- 本の感想
など、自分で自由に設定できます。
もしメモアプリで満足できなくなったら、パソコンなら「文書作成ソフト」を、スマホならより高機能なメモアプリをインストールして記録しましょう。
自分に合ったメモアプリを探すことも楽しくなりますよ。
書評サイト
デジタルの読書記録におすすめのツール、2つ目は「書評サイト」です。
「書評」というと固くなりますが、実際は読んだ本の感想を気軽に公開できるサイトのことです。
サイトによって記録できる項目は異なりますが、星の数で面白さを評価したり、感想を記録できたりします。
現在では次のように、様々な書評サイトが運営されています(サイト名をクリックするとページに飛べます)。
私は「ブクログ」に登録しています。
読んだ本が本棚に並ぶようにデザインされているため、見た目にも満足感が得られるんです。
また、参考になる登録者をフォローすることもでき、読書コミュニティの輪も広げられます。
「ブクログ」のほか、気になる書評サイトがあったら、ぜひ一度覗いてみましょう。
ブログ
デジタルの読書記録におすすめのツール、3つ目は「ブログ」です。
感想が長くなったり、感想を積極的に発信したいと思ったりしたら、ブログで感想を公開してみましょう。
ブログには「無料ブログ」と「有料ブログ」がありますが、将来的にお金を得られなくてもいいなら「無料ブログ」で十分です。
無料ブログなら登録してすぐに記事が書けるため、すぐに感想を公開したいという方にピッタリなんです。
またブログを更新し続けると、自然とブログに関する知識も得られます。
仕事に活かせる場合もあるため、将来的な投資としてもブログは役立ちます。
読書の感想を公開する「読書感想ブログ」の詳細については以下の記事でまとめているので、詳細を知りたい方はご覧ください。
各種SNS
デジタルの読書記録におすすめのツール、4つ目は「各種SNS」です。
「気軽に感想を投稿したい」という方には、各種SNSを読書記録として活用しましょう。
読書記録の投稿に使えるSNSは
- X
- BlueSky
- mixi2
など様々です。
個人的におすすめなのは、ゆるく居心地の良い「BlueSky」と、古参SNS「mixi」が進化した「mixi2」です。
ただSNSは、自分との相性がもっとも大切です。
最初は試しに登録してみて、様子を見ながら読書記録先として活用しましょう。
まとめ:長く続けて振り返ろう
ここまでご覧いただき、ありがとうございます。
今回は「読書記録はアナログかデジタルか」について解説しました。
読書記録は、長く続けてこそ意味があります。
記録がたまってきたら、ぜひ内容を振り返ってみましょう。
「こんなに読めたのか」という満足感を得られ、本の内容も思い出せるため、さらに本が読みたくなりますよ。
それでは、良き読書ライフをお送りください!
【参加中です!ボタンを押していただけると嬉しいです!】
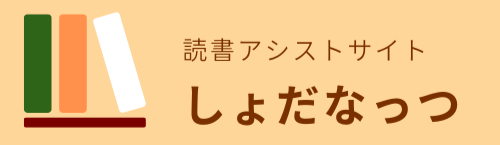




コメント